国や地域によって傾向は大きく異なるが、離婚は過去数十年の間に世界中でますます一般的になっている。世界的に見ると、粗離婚率(人口1,000人当たりの年間離婚件数)は1970年代から2000年代にかけて約2倍に上昇した。例えば、欧州連合(EU)の離婚率は、1964年の人口1,000人当たり約0.8から、2023年には2.0に上昇した。しかし、離婚のパターンは一様ではなく、各国の社会規範、法的枠組み、人口動態を反映している。離婚を測定する主な方法は2つある:
- 粗離婚率:ある年の人口1,000人当たりの離婚件数。これは人口における離婚の年間頻度を示す。
- 離婚率(Divorce-to-Marriage Ratio):婚姻件数に対する離婚件数の割合で、しばしばパーセンテージで表される(例:婚姻件数100件当たりの離婚件数)。これにより、結婚が最終的に離婚に至るおおよその生涯リスクがわかる。例えば、50%という比率は、結婚の約半数が離婚に至ることを示唆している。
これらの指標を文脈に沿って解釈することが重要である。粗率は、未婚人口の割合や年齢構成によって影響を受ける可能性がある。離婚率は、生涯離婚リスクを大まかに推定したもので、現在の結婚と離婚のパターンが一定であると仮定しているが、実際の生涯離婚率は、結婚コホートを時系列で追跡することによって算出される。それでも、これらの指標を合わせれば、離婚の有病率に関する有用なイメージが得られる。
国別離婚統計(最新データ)
以下の表は、信頼できるデータが入手可能な国の離婚率であり、最新のデータ年、粗離婚率、粗婚姻率、離婚に至った婚姻の推定割合(離婚対婚姻率)を含む。これにより、離婚普及率の国別内訳を知ることができる。
ヨーロッパ
ヨーロッパは世界で最も離婚率の高い国のひとつである。多くのヨーロッパ諸国や旧ソビエト諸国では20世紀後半に離婚が急増し、現在では結婚の40-90%が離婚に至っている。これとは対照的に、最近になって離婚が合法化あるいは正常化されたヨーロッパの数カ国は、離婚率がかなり低い。
ヨーロッパポルトガルとスペインは突出しており、結婚の90%以上が離婚に至ると推定され、世界で最も高い水準にある。対照的に、最近になって離婚が認められた伝統的なカトリック国(マルタ(2011年)、アイルランド(1996年)など)の離婚率はまだ非常に低く(1,000人あたり0.8未満)、離婚に至る婚姻件数は12~151件にすぎない。例えば、フランスでは結婚の約50%が離婚に至り、イギリスでは約41%、ドイツでは約39%である。北欧諸国では45~50%が離婚に至っている(例:スウェーデン~50%)。東欧諸国やソビエト連邦崩壊後の国の多くは離婚率が高い:例えばロシア(74%)やウクライナ(71%)。これらの国では、ソビエト時代とその後に離婚が急増した。一方、いくつかの東欧諸国は低い離婚率を維持している(ルーマニアは~22%、伝統的に保守的な規範のため)。全体として、ヨーロッパの粗離婚率は1,000人当たり約1~3人、中央値は1,000人当たり約1.5~2.5人であるが、婚姻率が異なるため、離婚対婚姻率は大きく異なる。イタリア(1970年)、スペイン(1981年)、アイルランド(1996年)、マルタ(2011年)で離婚が合法化され、これらの国々で長期的に離婚件数が増加した。
北米
北米の離婚率も比較的高いが、最近の傾向では低下している地域もある。
北米米国は長い間、主要国の中で最も粗離婚率の高い国のひとつであった(1980年代初頭に5.0近くのピークを記録)。2000年には1,000人当たり4.0人であったが、その後低下し、2020年現在では2.3人となっている。現在、米国では結婚の約42-45%が離婚に至ると推定されている。隣国のカナダも同様で、結婚のおよそ48%が離婚に至っている(~2008年現在)。カリブ海諸国と中央アメリカの中では、キューバが例外的に離婚率が高く、結婚の約56%が離婚に至っている。これとは対照的に、メキシコの粗離婚率(~1.0)はかなり低く、家族の伝統が強いため、メキシコの結婚のうち20~25%しか離婚に至らないと推定される(最近のデータに基づく概算)。ラテンアメリカのいくつかの国は、歴史的に離婚率が非常に低かった(最近まで離婚が禁止されていたり、珍しかったりしたケースもある)。例えば、チリは2004年に離婚が合法化されたばかりだが、2009年時点でも離婚率は低かった(1,000人当たり0.7人、婚姻件数で~21%)。中央アメリカの多くの国(グアテマラ、ホンジュラスなど)では、人口1,000人当たりの離婚率は1以下と報告されており、法的離婚に至る結婚の割合は10%以下ということになる(非公式の別居はもっと高いかもしれないが)。
アジア
アジアは、多様な文化と法律を反映して、最も幅広い離婚率を示している。東アジアやユーラシア大陸の一部の国々は離婚率が最も高く、南アジアは最も低い。
アジア東アジアのいくつかの国では急激な社会変化が起こり、現在では離婚率が高くなっている。韓国の離婚率は1990年代から2000年代にかけて劇的に上昇し、2019年には結婚の約47%が離婚に至っている。中国の離婚率も同様に2000年代に上昇し、都市化と離婚手続きの緩和を反映して、2018年には1,000組あたり約3.2組(婚姻件数44%)となった--実際、中国の離婚件数は2019年までの16年間、毎年増加している。(2021年に新しい「クーリング・オフ」法が施行され、中国の離婚届は急激に減少したが、これが長続きするのか、単に離婚が遅れるだけなのかは議論がある)日本の離婚率は2002年頃にピークに達し、その後低下した。2019年現在、日本の離婚率は1,000人当たり1.7人で、結婚のおよそ35%が離婚に至っている。東南アジアでは、宗教的・文化的規範もあり、離婚率は中程度から低い傾向にある。例えば、ベトナムでは1,000人当たりの離婚件数はわずか0.4件で、結婚のうち7%が離婚に至っている。インドネシアも、イスラム教徒の人口が多いにもかかわらず、粗離婚率は低い(~1.2)(イスラム教では離婚を認めているが、実際にはまだまれである)。南アジアは世界で最も離婚率が低い。インドの粗離婚率は1,000人当たりわずか0.1人で、インドの結婚のうち法的離婚に至るのはわずか1%程度である。この極めて低い離婚率は、離婚に対する強い社会的烙印、拡大家族の圧力、インドの法的ハードルに起因している。他の南アジア諸国や中東諸国でも離婚率は非常に低い(例えばスリランカは1000組あたり0.15組、結婚の数パーセント)。例えば、サウジアラビアとカザフスタン(イスラム教徒の多い中央アジアの国)では、結婚の30~40%が離婚に至っている。湾岸諸国では離婚は比較的一般的で、例えばクウェートでは2010年に約42%であった。特にフィリピン(とバチカン)は、離婚が完全に違法である唯一の国として際立っており、その結果、結婚の実質的な0%が合法的に離婚に終わっている(取り消しは可能だが、まれである)。このような法的禁止により、たとえ別居が続いたとしても、記録上の離婚率はゼロに保たれている。
アフリカ
アフリカにおける信頼できる離婚統計は乏しいが、入手可能なデータによれば、一部の例外を除き、離婚率は概して低い。アフリカの結婚の多くは慣習的または宗教的なものであり、正式な法制度の外で解消されることがあるため、公式な離婚件数は少ない。
アフリカ:多くのアフリカ諸国では、粗離婚率は1,000人当たり1未満であり、正式な離婚が比較的少ないことを示している。例えば、記録されやすいケースの1つである南アフリカの2009年の離婚件数は1,000人当たりわずか0.6件であり、これは結婚の約17%が離婚に至ったことに相当する。アフリカの一部では離婚に対する社会的/宗教的不支持が強いこと、裁判では決着がつかないような非公式な別居や一夫多妻制が普及していること、離婚を成立させるのが(特に女性にとって)現実的に困難であることなどである。イスラム法が結婚に影響する北アフリカや中東では、離婚は法的に認められているが、条件付きであることが多い。例えばエジプトでは、近年離婚件数が増加しており(2021年には1000人当たり2.4件)、これはアフリカで最も高い離婚率のひとつである。モーリシャス(17%)やモロッコ(~15-20%)のような他のアフリカ諸国の離婚率は中程度である。一般的に、アフリカの社会は夫婦関係の安定を重視しており、多くの離婚は公的な統計に基づかずに(例えばコミュニティの長老を介して)行われている。サハラ以南のアフリカの一部では、(社会経済的ストレスや寡婦化などの要因から)婚姻関係の不安定性が高い場合があるが、これらは必ずしも「離婚」としてデータに登録されるわけではない。データが存在する場合、都市部や高学歴層の離婚率が農村部よりも高いというパターンがよく見られるが、これは夫婦の別居の自由度が高いことを反映している。
オセアニア
オセアニアの離婚パターンは欧米諸国と似ている。
オセアニア:オーストラリアとニュージーランドの離婚率はヨーロッパと北米に匹敵する。オーストラリアとニュージーランドでは、結婚のおよそ40-45%が離婚に至ると予想されている。例えばニュージーランドでは、2022年の粗離婚率は1,000人当たり1.6人であり、同年の既婚夫婦1,000人当たりの離婚件数は約7.6件であった。両国とも20世紀後半にかけて離婚が増加したが、近年は婚姻率の低下に伴い、離婚率は安定またはわずかに減少している。対照的に、太平洋諸島の多くの小国(フィジー、サモアなど)は、より保守的な家族構成であり、データも限られているが、逸話的証拠によれば、離婚発生率は比較的低い(1,000人に1人以下であることが多い)。
テーブルノート データは入手可能な最新の年(括弧内)を反映。「離婚に至った婚姻数の%」は、その年の離婚数÷婚姻数×100で算出(生涯離婚リスクの高位推定値)。実際の生涯離婚確率は、特に変化の激しい国では若干異なるかもしれない。とはいえ、このパーセンテージは比較指標として有用である。これらの数値については、国連人口統計年鑑や各国の統計機関など、権威ある情報源を引用している。一般に、世界の離婚率は1,000人当たり0.5人以下(少数の離婚率の低い社会)から、高い国では3~4人程度まで幅があり、離婚に至る結婚の割合は5%以下から90%以上までと、法律や文化の両極端を反映した驚くべき幅がある。
世界で最も高い離婚率と最も低い離婚率
世界的に見て、粗離婚率(人口1,000人当たり)が最も高いのは、ソビエト連邦崩壊後の国家、ヨーロッパの一部、その他いくつかの地域である。国連の最新データによると、年間離婚率の上位は以下の通りである:
- 北マケドニア:人口1,000人当たりの離婚件数9.6件(2023年)-最近の急増により、このバルカンの小国がトップに立つ。 2023年のこの異常に高い離婚率は、パンデミック後に処理された離婚の滞留やその他の異常によるものかもしれない)。
- モルディブ1,000人あたり5.5人(2020年) - 歴史的にモルディブの離婚率は極めて高く(2002年のピーク時には1,000人あたり10.97人で、ギネス世界記録に認定された54)、これは多重結婚の文化的規範に起因している。近年でも、人口1,000人当たりの離婚件数は5件以上で世界トップである。
- ベラルーシ、グルジア、モルドバ:1,000人当たり約3.7~3.8人(2021~2022年)。旧ソビエト連邦のいくつかの共和国が上位を占めているが、これはソビエト連邦崩壊後の社会的離婚容認率の高さと経済的ストレスを反映している。例えば、ベラルーシは1,000人当たり3.7人、モルドバは3.7人である。
- ラトビア、リトアニア:~2.5~2.9/1,000(2022年)。バルト三国の離婚率は一貫して高く、ラトビアは現在EUで最も高い2.8である。
- アメリカ~米国はかつてはトップクラスだったが、現在は減少し、東欧に比べれば緩やかである。
生涯」離婚リスク(離婚に至る結婚の割合)を見ると、上位の国々は若干異なっており、結婚率の低さが影響しているところもあることが浮き彫りになっている。離婚率の高い国は以下の通り:
- ポルトガル:結婚の92~94%が離婚に至る。ポルトガルの年間離婚件数は、結婚件数の少なさと離婚しやすい法律の影響もあり、結婚件数とほぼ同じである。
- スペイン:結婚の85%が離婚に至る。1981年に離婚が合法化された後、スペインの離婚率は急上昇し、新婚が比較的少ないこともあり、最近のデータでは離婚率は極めて高い。
- ロシア:73~74%、ウクライナ:~71%、ベラルーシ:~60~65%(推定)。これらのスラブ諸国は結婚回転率が高く、結婚件数は多いが、その割に離婚件数が多い。
- キューバ:~56%、フランス:~51%、スウェーデン:50%:~キューバ:~56%、フランス:~51%、スウェーデン:50%。多くの欧米諸国は50%付近に集中しており、これは結婚のおよそ半分が最終的に解消することを意味する(よく言われる「結婚の半分が離婚に至る」というのは、アメリカ、フランス、イギリスなどでほぼ当てはまる)。
対照的に、離婚率が最も低いのは、離婚に法的または文化的な障壁がある社会である。以下はその例である:
- インド結婚の約1%しか離婚に至っていない。インドの粗離婚率(~0.1)は、どこの国よりも低い。強いスティグマと結婚に耐えることへの期待から、離婚は非常に少ない。
- ブータン、スリランカ、ベトナム:結婚のうち離婚に至るのは5-7%に過ぎない。これらのアジア諸国の離婚率は1,000人あたり0.5%以下である。例えばスリランカでは0.15であり、離婚には長期の法的手続きを要することが多い。
- コロンビアと多くのアフリカ諸国:離婚の可能性は10-20%であることが多い。カトリックや共同体の影響が強いアフリカやラテンアメリカの多くの国(グアテマラ、コンゴ、ナイジェリアなど)では、離婚件数が非常に少ないと報告されている。
- フィリピンとバチカン市国:0%(法的離婚不可)。フィリピンでは、結婚を解消できるのは婚約破棄か死亡のみである。当然のことながら、公式な離婚率は事実上ゼロであり、世界の離婚ランキングではしばしば最下位に位置している。
図:離婚率の世界地図(国別の「離婚する確率」)。暖色系(赤)は離婚率または離婚の可能性が高いことを示し、寒色系(緑)は離婚率が低いことを示す。灰色はデータ不足を示す。この地図は、離婚が旧ソ連、ヨーロッパの一部、北米で最も多く、南アジア、アフリカの一部、東南アジアの一部の国で最も少ないことを強調している。
地図とデータが示すとおりだ、 離婚率は地域によって大きく異なる.一般的に、先進地域やよりリベラルな社会規範を持つ地域(ヨーロッパ、北米、オセアニア)の離婚率は高く、より伝統的または制限的な規範を持つ発展途上地域(南アジア、中東、アフリカ)の離婚率は低い。しかし、特筆すべき例外もある。例えば、裕福な東アジア諸国(日本、韓国)の離婚率は中程度であり、(旧ソビエト圏のような)貧しい国の中には、独自の歴史的要因により離婚率が高い国もある。次に述べるように、文化的態度、宗教、法体系がこれらの結果に大きく影響している。
主要国の過去の離婚傾向
多くの国の離婚率は、過去50年以上にわたって逆U字型の軌跡をたどってきた。1970年代から1990年代にかけて急上昇し、2000年代にはプラトーか減少に転じた。ピークの時期や高さは国によって異なり、さまざまな社会変化を反映している。下の図1は、世界各国の離婚率の推移を示したもので、こうした多様なパターンを浮き彫りにしている。
図1:特定国の離婚率の推移(人口1,000人当たりの年間離婚件数)(1960~2020年)。多くの欧米諸国(アメリカ、イギリス、ノルウェーなど)の離婚率は1960年代から上昇し、1970年代から1980年代にかけてピークを迎え、その後低下した。東アジアや東欧の一部の国(韓国、エストニア、ポーランド)は、離婚がより受け入れられるようになったため、ピークが遅くなった(2000年代初め頃)。トルコのように、低いベースから2010年代に入って着実に上昇している国もある。(データ出典:OECD/UN、Our World in Data.)
米国では、無過失離婚法の導入と性別役割分担の変化に伴い、粗離婚率は1960年の約2.2%から1981年には史上最高の1,000人当たり5.3%まで上昇した71 。それ以来、離婚率は着実に低下し、2021年には過去50年間で最低の2.5まで低下した。この減少の一因は、若い世代が晩婚化し、より選択的に結婚するようになり、より安定した結婚生活を送るようになったことにある。米国の初婚の離婚リスクはいくらか低下している(現在、全体で約40~45%と推定)。同様に、カナダとオーストラリアも1980年代にピークを迎え、その後は減少している。例えば、オーストラリアの離婚率は、1975年に無過失離婚が始まった後に急上昇し、その後安定した。オーストラリアで離婚に至る結婚の割合は、1980年代の約50%から、現在では~41%まで減少している。
西ヨーロッパでは、ほとんどの国で1970年から1990年にかけて離婚率が急上昇した。英国は1990年代半ばに1,000人当たり約3件の離婚でピークに達したが(1990年代の離婚緩和のための改革後)、その後は約1.8件まで低下した。北欧諸国は最も早い時期に離婚件数が増加した(例えば、スウェーデンは1980年代までに1,000人当たり~2.5件を記録し、現在も2.0~2.5件前後である)。南ヨーロッパは遅れており、イタリア、スペイン、ポルトガルなどの国々は、離婚が合法化されるまで離婚率が非常に低かった(スペイン1981年、ポルトガル1975年、イタリア1970年)。合法化後、これらの国では離婚率が急上昇した:スペインの離婚率は、特に2005年に制定された法律で手続きが緩和された後に急上昇し、現在の高い離婚率の一因となっている。ポルトガルの離婚率も1990年代から2000年代にかけて急上昇し、現在では世界最高水準にある。興味深いことに、欧米諸国では最近、離婚率が低下している国もある。例えば、ドイツ、オランダ、フランスでは、2000年代初頭以降、粗離婚率がわずかに低下している。これは、そもそも結婚する人が減ったこと(離婚できる人が減ったこと)、同棲が増えたこと、結婚年齢が高くなったこと(離婚リスクが低くなったこと)などが原因であると考えられている。EU全体の離婚率は2006年頃に2.1でピークを迎え、その後2019年までに1.8~2.0までわずかに低下した。
東欧と旧ソ連では、1990年代の移行期に離婚率が非常に高くなった。ロシアとウクライナは1990年代から2000年代にかけて、ソビエト連邦崩壊後の社会的混乱と新たな自由を反映して、1,000人当たり4~5人前後の粗率でピークを迎えた。その後、ロシアの婚姻率は約3.9(2020年時点)まで緩やかになったが、婚姻件数と比較すると依然として高い。バルト三国(エストニア、ラトビア、リトアニア)はいずれも1990年代後半に離婚率が急上昇し、高止まりしている(ラトビアの2023年の離婚率2.8は欧州で最も高い水準)。東欧諸国の中には、最近離婚率が低下している国もある(例えばポーランドは2006年頃にピークを迎え、その後わずかに低下した)。これは、家族を重視する文化や、若年層の結婚が減少しているためと思われる(ポーランドは依然として欧州で最も結婚率の高い国のひとつである)。
アジアの傾向は多様だ。日本の離婚率は第二次世界大戦後に徐々に上昇し、2002年には~2.1に達したが、人口の高齢化と若年層の結婚減少に伴い、2019年には~1.6~1.7まで低下した。韓国の離婚率は1990年の1.1%から2003年には3.5%へと3倍に上昇し、2010年には2.2%にまで低下した。韓国と日本のこのパターン(ピークとその後の減少)は、世代交代(1980年代から90年代に結婚したコーホートは離婚率が高かったが、若いコーホートは結婚が減り、少し安定している)によって一部説明できる。中国は2000年代を通じて離婚率が着実に上昇していることが注目される。1980年代の非常に低いベースから、中国の粗離婚率は2018年までに3.2に達した。中国政府は最近、2021年に30日間の離婚待機期間を導入したが、その直後には登録離婚件数が70%減少したと報告されている。しかしこれは、真の行動変化というよりは、離婚の遅れや未登録の別居を示すものかもしれない(一部の中国人カップルは法律が施行される前に離婚を急ぎ、2020年の数値が急上昇し、その後2021年には低下した)。長期的に見れば、中国の傾向は、都市部における個人主義の高まりと離婚にまつわるスティグマの減少を反映している。これとは対照的に、インドの離婚率は長期にわたって一貫して極小のままである。これに匹敵するような「離婚ブーム」はなく、歴史的なスティグマが離婚率をゼロに近づけてきた(ただし、インドの都市部では近年、離婚件数が徐々に増加している)。
多くの中東・北アフリカ諸国には長期的なデータがないが、エジプトやヨルダンのように2010年代に離婚件数が増加している国もある。例えば、エジプトの離婚率は2010年代を通じて上昇し、2021年には最高を記録した(1,000人当たり2.4人)。アラブ首長国連邦(UAE)、カタール、クウェートなどの湾岸諸国は、1990年代から2000年代にかけて離婚率が高かったと報告されており(カタールのピークは2005年ごろで、1,000人当たり約2.2人、クウェートはさらに高かった)84 、その後、ある程度安定した。こうした傾向は、近代化や女性の教育が向上し、不幸な結婚に終止符を打つ意欲が高まったことと一致することが多い。
アフリカでは、過去のデータは限られている。しかし、逸話的証拠によると、南部アフリカ諸国の中には2000年以降に離婚が一般的になった国もある(例えば、ボツワナと南アフリカは1990年代に増加し、その後わずかに減少した)。南アフリカの離婚記録は2004年以降徐々に減少しているが、これはおそらく正式な結婚が減り、同棲が増えたためであろう。これとは対照的に、エチオピアやナイジェリアのような国では、別居率は高いかもしれないが、正式な離婚率は歴史的に見ても非常に低い。
要約すると、主要先進国は「離婚革命」のピークをほぼ過ぎた。20世紀後半にかけて上昇した離婚率は、21世紀には頭打ちか減少に転じている。発展途上国にはさまざまな段階がある。2000年代に離婚率の急上昇を経験し、現在は横ばいになっている国(特に東アジア、ラテンアメリカの一部)もあれば、永続的な文化的制約のために大幅な上昇に至っていない国(南アジア、アフリカの一部)もある。
地域と経済パターン
大陸や経済グループ間で比較すると、離婚の有病率に明確なパターンが現れている:
ヨーロッパと北米: これらの高所得地域の離婚率は中程度から高い。近年のOECD高所得国の平均粗離婚率は1,000人当たり約1.8人である。ヨーロッパでは、EUの平均は約2.0である。ほぼすべての欧米諸国は無過失離婚を認めており、法的障壁も最小限であるため、離婚率はかなり高い。しかし、このグループ内でもばらつきがある:北欧・西欧(および北米・オセアニア)の離婚率は40~50%前後であるのに対し、伝統的にカトリックや正教の国(アイルランド、ポーランド、イタリア)の離婚率は、上昇傾向にあるものの、低い。経済発展と都市化は離婚率の上昇と相関する傾向があり、これは女性の経済的自立と社会的セーフティネットが結婚からの離脱をより現実的なものにしているからである。実際、女性の教育や労働力参加が進んでいる国ほど離婚率が高いという研究結果もある。これは、例えばスカンジナビア(男女平等が高く、離婚率が相対的に高い)対後進国で明らかである。例えば、ロシアとその近隣諸国(高位中所得国)は、社会経済的緊張と政策に対する宗教的影響力の弱さにより、離婚率において多くの富裕国を上回っている。
アジアアジアは、離婚率が最も低い社会と最も高い社会の両方を含むため、一般化に逆らう。一般に、東アジアや中央アジア諸国(韓国、中国、カザフスタンなど)の離婚率は欧米諸国並みとなっている。対照的に、南アジア(インド、バングラデシュ、パキスタン)は、文化的規範(家父長的家族制度、スティグマ、見合い結婚の伝統)のため、極めて離婚率が低いままである。東南アジアはその中間に位置する。インドネシアやマレーシアのようなイスラム教徒が多い国では、離婚の記録は少ないが、イスラム法は男性の離婚を比較的容易に認めている(これが非正規離婚を増加させている可能性がある)。これらの地域では、家族の結束と離婚にまつわる社会的羞恥心が離婚率を低く抑えている。例えば、ベトナムやタイの離婚率が低いのは、拡大家族が夫婦間の問題を調停することが多いためでもある。アジアの貧しい農耕社会では離婚率が低いが、これは家族が経済的な単位であり、女性が結婚以外のサポートに欠ける可能性があるためである。しかし、経済が成長し、女性が機会を得ると、離婚は増加する傾向にある(例えば、中国の都市部における離婚の急増は、経済の自由化と同時期であった)。注目すべきは、(これまでのフィリピンのように)離婚法が制限的であったり、別居の要件が長かったりする国は、当然ながら離婚率が低いということである。
中東と北アフリカ:この地域の離婚率は中程度であるが、ばらつきが大きい。一般に、湾岸アラブ諸国(クウェート、カタール、UAEなど)や北アフリカ諸国では、1,000人当たり1~2件程度と報告されており、ヨーロッパほどではないが、南アジアよりは高い。文化的規範は、女性が離婚を切り出すことを強く抑制しているが、(イスラム法では)男性が妻を拒絶することができるため、男性が切り出す離婚率が高くなる可能性がある。男女不平等も一役買っている。皮肉なことに、男女不平等が大きい中東諸国の中には、離婚率が比較的高い国もある(男性が自由に離婚できる一方で、女性はその結果に耐えているため)。逆に、イエメンやシリアのように離婚率が非常に低い国は、社会的圧力と女性が離婚することの難しさの両方を反映しているのかもしれない。近年、法改正によって離婚が容易になり、女性の教育水準が向上したため、近代化によって、よりリベラルな地域(チュニジア、イラン、トルコなど)では離婚がわずかに増加している。例えば、トルコの離婚率は1,000人当たり1.7件に過ぎないが、伝統的な家族構造が進化するにつれて上昇の一途をたどっている。
ラテンアメリカラテンアメリカ諸国は、歴史的にカトリックの影響で離婚率が低かった(20世紀後半まで離婚を禁止していた国も多い)。過去数十年の間に、ラテンアメリカ全土で離婚が合法化され、より一般的になったが、離婚率は一般的にヨーロッパ/北米より低い。ほとんどのラテン諸国の粗離婚率は、1,000人あたり1~2人程度である(例:ブラジル~1.4人、コロンビア~0.7人、コスタリカ2.6人)。キューバは、キューバ革命以来の世俗的、社会的に自由な政策に起因することが多い、世界で最も離婚率の高い国のひとつである(1,000人当たり2.5人以上、結婚の50%以上が離婚している)。ドミニカ共和国とプエルトリコも1,000人当たり2.4~2.6人と比較的高い。一方、チリやペルーのような文化的に保守的な国は依然として低い(チリは離婚が合法化された後、2010年代に1,000人当たり1.0人を超えたのみ)。全体として、ラテンアメリカが都市化し、女性の権利が向上するにつれて、離婚率は徐々に上昇しているが、家族中心の文化によって、離婚率は欧米の水準を下回っている。重要なのは、ラテンアメリカでは非公式の別居や合意による結婚が一般的であり、離婚統計に反映されない場合があることだ。多くのカップルは法的な離婚をせずに単に別居しているか、そもそも正式に結婚していないため、公式の数字に影響を与えている。
アフリカアフリカは最もデータが少ない地域だが、伝統的な規範は夫婦関係の安定を支持している。多くのアフリカ諸国は二重婚姻制度(民法と慣習法)を採用しており、慣習法上の離婚は公式にはカウントされていない可能性がある。データがある場合(南アフリカ、エジプト、モーリシャス、ケニア)、粗率はおおよそ0.5~2.0である。一般的に、サハラ以南のアフリカでは離婚率が低い。例えば、ナイジェリアとエチオピアの離婚率は極めて低い。例外はボツワナで、1990年代にはアフリカとしては異例に高い離婚率(母系社会構造のためか、結婚の10%以上が離婚に至っている)を記録しているが、データは限られている。アフリカの社会では、花嫁の値段(持参金)やコミュニティの調停といった要素が離婚を抑制している。しかし、一夫多妻制や非婚同棲は、「離婚」として捕らえられない関係解消につながる可能性がある。注目すべきは、アフリカで女性の識字率や雇用が高い国(南アフリカ、モーリシャスなど)は、女性の自主性が低い国よりも離婚率がやや高い傾向があることだ。それでも、南アフリカでさえ、離婚率は欧米諸国と比べると控えめである。経済的ストレスは、時に家族を崩壊させるが、結婚を経済的パートナーシップとして必要なものにし、人々がそこから離れたがらないようにする。
経済分類の観点からは、高所得国の方が低所得国よりも平均して離婚率が高い。先進国は公的な離婚率が高いだけでなく、離婚した個人を支援するための自由な法律や社会的セーフティネットも充実している。対照的に、低所得国では、結婚はしばしば家族の名誉、女性の経済的安定、社会的地位と結びついており、離婚を抑制している。例えば、離婚率の低い上位10カ国はすべて、国連のジェンダー不平等指数(女性の役割がより伝統的で制限的であることを示す)のスコアが低い。このことは、離婚率が非常に低いということは、夫婦円満というよりも、女性のエンパワーメントが限られているか、法的なハードルが高いことの表れであることを示唆している。実際、比較してみると、離婚率の低い国の多く(ウズベキスタン、モンゴル、パキスタンなど)は男女平等の順位が低いのに対し、離婚率の高い国の中には、比較的男女平等な国(スウェーデン、ベルギーなど)もあるが、そうでない国(ロシア、ベラルーシ)もある。要するに、個人の自由と男女平等が高まれば、ある程度までは離婚率が上昇する傾向があるが、極端に離婚率が高いのは、中所得国の社会的不安定や規範の進化に起因することもある。離婚率の高い社会にはさまざまな経済レベルがあるが、共通しているのは、結婚を終わらせることを文化的に受け入れていることである。逆に、離婚率の低い社会では、離婚にまつわる厳しい法的/宗教的制約や社会的罰則を強いていることが多い。
社会的、法的、文化的背景
離婚は真空地帯で発生するものではなく、社会の規範、法律、結婚に対する考え方に深く影響される。ここでは、社会的、法律的、文化的な要因が離婚率の違いにどのような影響を与えているかを検証する:
文化的/宗教的規範:おそらく離婚率を最も強く左右するのは、結婚の永続性に対する文化的態度であろう。結婚が神聖で不溶の結合とみなされる社会(多くの場合、宗教に支えられている)では、離婚はまれである。例えば、インドやイスラム教徒が多数を占める多くの国では、離婚にはかなりのスティグマがつきまとう。家族は恥を避けるために、たとえ不幸な状況や虐待があったとしても、夫婦が一緒にいるよう圧力をかけることがある。インドでは、結婚の概念は「一生もの」であることが多く、離婚は社会的スティグマとなりうるため、結婚が破綻するのはわずか1%にすぎない。同様に、歴史的にカトリック教徒が多い国(フィリピン、アイルランド、ポーランドなど)では、離婚に反対する宗教的教義があったため、法改正が行われるまで離婚率は極めて低かった。対照的に、個人の幸福や個人的な充足感を重視する文化圏では、離婚率が高くなる傾向がある。今日のヨーロッパと北米の多くでは、離婚は残念なことではあるが、社会的に受け入れられ、かなり一般的である。この受容は世俗化によって1960年代以降に著しく拡大した。例えば、西ヨーロッパにおける世俗主義の台頭は、離婚の増加に対応している(例えば、スペインは20世紀後半にカトリックの独裁政権から世俗的な民主主義へと移行し、結婚の85%まで離婚が急増した)。儒教の影響を受けた東アジア諸国(中国、韓国、日本)は、伝統的に家族の結束を重んじ、離婚が少なかったが、これらの社会が近代化し、より個人主義的になるにつれ、離婚はタブー視されなくなった。国内でも、宗教的なコミュニティや農村部よりも、都市部の世俗的なコミュニティの方が離婚が一般的であることは注目に値する。例えば米国では、宗教的に離婚を奨励しないため、福音主義的なキリスト教コミュニティでは離婚率が全国平均よりやや低いことが多いが、リベラルなコミュニティでは離婚率が高い。
法的アクセスと改革:離婚のしやすさ、しにくさは重要な要素である。離婚が違法または厳しく制限されている国では、当然、離婚率は極めて低くなる。離婚が認められていないフィリピンとバチカン市国では、公式な離婚率はゼロである45 。長い別居期間、特定の理由(過失に基づく離婚)、または双方の同意が必要な国では、離婚率は一般的に、短時間で過失のない離婚ができる国よりも低い。例えば、マルタは2011年に離婚を合法化した際、当初は4年間の別居を義務づけ、離婚率を低く抑えた。アイルランドは現在も別居期間を定めており(最近4年から2年に短縮された)、このことも低離婚率(~15%)の一因となっている。これとは対照的に、無過失で迅速に離婚できる国の離婚率は高い傾向にある。米国(1970年代)やオーストラリア(1975年)などで無過失離婚法が導入されると、夫婦が不義を証明する必要がなくなったため、離婚申請が一気に急増した。今日、ほとんどの欧米諸国では、理由なく双方の合意による離婚が認められており、離婚件数の増加が常態化している。手続きを簡略化している国もある(例えば、ノルウェーとスウェーデンは、短期間の待機期間の後、オンライン申請を許可している)。比較分析によると、離婚手続きが最も簡単で負担が少ない国は、ノルウェー、スウェーデン、スペイン、メキシコ、スロベニア、アルゼンチンなどである。逆に、離婚法が非常に複雑な国、例えばパキスタン(女性は裁判に出廷して理由を証明しなければならないが、男性は一方的に否認することができる)やエジプト(無過失「クーラ」離婚のために女性は経済的権利を放棄しなければならない)では、離婚件数が少なかったり、男性優位の離婚届出が多かったりする。法改正は直ちに統計に影響を与える:チリでは2004年まで法的離婚はゼロに等しかったが、合法化後、潜在的な需要により何千もの離婚が登録され、離婚率が上昇した。ブラジルは2010年に別居期間を撤廃した後、離婚件数が増加した。中国では、最近の冷却期間法が離婚プロセスに摩擦をもたらし、離婚件数を一時的に抑制したようだ。このように、法制度がいかに離婚に優しいか、あるいは離婚を嫌うかが大きな役割を果たしている。
女性の権利と経済的自立:一貫して見られるのは、女性が社会経済的な力を得るにつれて離婚率が上昇するということである。女性が教育を受け、キャリアを持ち、法的権利を持つようになると、不幸な結婚や抑圧的な結婚に耐えられなくなる。歴史的に、女性が財産を持ったり自活できない社会では、離婚は女性を貧困や社会的追放に陥れることが多かったため、離婚はまれだった。こうした障壁が取り除かれるにつれ、離婚は増加した。例えば、欧米諸国では1970年代に離婚が急増したが、これは女性解放運動が起こり、働く女性が増えたことと相関している(米国では、多数の女性が労働力になり、結婚をめぐる規範が変化した時期に離婚がピークに達した)。東アジアでは、1990年代から2000年代にかけて離婚が増加し、韓国、中国、台湾などでは女性の教育と労働参加が進んだ。中東では、女性の識字率が高い国(イラン、トルコなど)は、女性の力が弱い国(離婚率が非常に低いイエメンなど)よりも離婚率が高いというデータがある。例えば、米国では離婚のおよそ70%が女性によって申し立てられているが、これは他の先進国でも見られるパターンであり、女性の自立が進むにつれて、不満足な結婚生活に終止符を打つ意欲が高まっていることを示唆している。一方、アラブ世界の一部のように、(法律や規範により)離婚の大部分が男性主導で行われる地域では、離婚は異なる社会的意味を持つかもしれない(離婚率が高いということは、男性が頻繁に離婚し再婚していることを示す場合もある)。全体として、法的権利の改善(夫婦財産法や養育費の執行など)や社会的支援(離婚した女性に対するスティグマの軽減など)は、現実的な障壁を取り除くことで、離婚率の向上に寄与する。
経済的ストレスと都市化:直感に反して、繁栄と貧困は離婚にさまざまな影響を与える。経済的安定は離婚を促進する。同時に、経済的ストレス(失業、インフレ)は夫婦関係を緊張させ、破綻に導く。例えば、ソビエト連邦崩壊後、経済の混乱が夫婦関係を不安定にした可能性が高く、ロシアの離婚率は1990年代の経済危機で急上昇した。ギリシャでは、最近の金融危機で離婚が増加したと言われている。一方、不況は、夫婦が費用のかかる法的手続きを遅らせたり、世帯分離をする余裕がなかったりすると、離婚率を一時的に低下させることもある。2008年の世界同時不況では、離婚率がわずかに低下した国もあった。都市化は離婚を増加させる傾向がある。都市では伝統的な家族の監視が弱くなり、人々はより多様なライフスタイル(と誘惑)にさらされる。都市はまた、離婚した人々により多くの匿名性と支援ネットワークを提供する。例えば、中国の離婚率が最も高いのは上海や北京のような大都市であるのに対し、農村の離婚率ははるかに低い。
社会的期待の変化:現代の結婚は、伝統的な功利主義的結婚とは異なる期待(感情的充足、役割分担)を持っていることが多い。期待が高まるにつれて、不満足な結婚生活に対する許容度が下がり、離婚が増えると主張する学者もいる。愛と自己実現に基づく結婚へのシフトは、そのようなニーズが満たされない場合、離婚の増加につながる可能性がある。世界の若い世代は一般的に、離婚に対する考え方が親よりもリベラルである。国連の世界的な概観によると、2000年代には、1970年代と比較して、30代後半までに離婚/別居する人の数が2倍になっている。これは、法的な変化だけでなく、不幸な結婚にとどまる必要はないという社会的受容も反映している。また、アジアのような地域では、お見合い結婚が減少し、恋愛結婚が増加している。
同棲の影響:多くの欧米諸国では、同棲(未婚での同居)の増加が離婚統計に影響を与えている。同棲は「お試し婚」や結婚の代替としての役割を果たすこともある。一部の国(スウェーデン、フランスなど)では、多くのカップルが結婚せずに同棲し、子供まで作っている。こうしたカップルの中には、離婚統計に載ることなく破局するものもある。同棲は婚姻率の低下に寄与しており、その結果、粗離婚率も低下している(もともと結婚する人が少ないため)。同棲は、結婚前の弱い関係を淘汰し(より安定した結婚につながる)、あるいは、結婚して離婚したはずの人々が単に同棲し、代わりに別れるという変化を反映しているかもしれない。全体として、ヨーロッパとアメリカにおける同棲の増加は、離婚率が最近横ばいか低下している理由のひとつである。
政策と支援制度:離婚に影響を与える政策を積極的に実施している政府もある。例えば、(スウェーデンや米国のいくつかの州のように)カウンセリングや調停を義務づけることで、衝動的な離婚を減らすことができるかもしれない。逆に、ひとり親を支援する福祉政策が離婚をより現実的なものにすることもある。子どもの親権や扶養に関する法律も一役買っている。法律が子どもや収入の少ない配偶者の扶養を保証すれば、配偶者は離婚をより自由に感じられるかもしれない。そのような支援がない国では、親(特に母親)は子どものために結婚生活を続けるかもしれない。国家がセーフティネットを提供している国ほど離婚が多いというデータもある(例えば、北欧の手厚い福祉は離婚が多いことと一致している。)一部の国(特にマレーシアやインドネシア)では、離婚手続きを厳格化したり、地域和解プログラムによって家族を強化しようとしているが、その結果はさまざまである。COVID-19の大流行は、政策と状況が相互に作用した最近の例である。当初、戸締まりによって2020年の離婚件数は世界的に減少した(裁判所が閉鎖され、夫婦は別れを先延ばしにした)。しかし、地域によっては、その後、鬱積した需要が解放され、離婚件数が回復した(例えば、ラトビアの離婚率は、2020年の落ち込みの後、2021-22年に急上昇した)。
まとめると、離婚率を理解するためには社会的背景が極めて重要である。離婚率の高い社会は一般的に、世俗的な態度、利用しやすい法的手続き、男女平等の拡大、個人の選択重視を特徴とする。離婚率の低い社会は、宗教的あるいは氏族的な統制が強く、法的な障害があり、(特に女性にとって)離婚に対する社会的あるいは経済的なペナルティが大きいことが多い。低離婚国の人々が夫婦関係の破綻や衝突を経験しないわけではなく、むしろ結婚生活を続けなければならないというプレッシャー(または離婚する仕組みの欠如)が、結婚生活を書類上そのまま維持しているのである。一方、離婚率の高い国では、結婚生活に不満がある場合、結婚を解消するための支援制度や社会的受容があることが多い。一般的に、その国の女性の教育水準が高いほど、その国の離婚率は高い。社会科学者たちはまた、離婚に対する態度が離婚率に影響し、また影響されることにも注目している。社会で離婚が一般的になればなるほど、離婚はさらにスティグマを失い、正常化のフィードバック・ループが生まれるのだ。
結論と要点
世界の離婚率は、文化的価値観、法的枠組み、経済状況、社会変動が複雑に絡み合っていることを反映している。この包括的な概観から、いくつかの重要な発見が得られた:
- 世界的な傾向20世紀後半は欧米諸国を中心に世界的に離婚率が上昇したが、21世紀に入ってその傾向は二極化している。多くの高所得国では2000年以降、離婚件数は安定または減少しているが、一部の中所得国では依然として増加傾向にある。2020年代の時点で、世界の粗離婚率の平均はおよそ1,000人に1~2人だが、この平均は大きなばらつきを隠している。
- 最も高い割合離婚率が最も高い国は、東ヨーロッパ(旧ソビエト)、西ヨーロッパの一部、そして新世界のいくつかの国々である。離婚に至る結婚の割合で見ると、ポルトガル(~92%)とスペイン(~85%)がトップで、ロシア(~74%)、ベルギー(~70%)*、キューバ(~56%)といった国々がそれに続く。これらの国は、結婚率が非常に低いか、離婚に非常に寛容な国である。年間粗離婚率で見ると、上位にはモルディブ、カザフスタン/ベラルーシ/グルジア(~3.5~3.8)、そして最近では異常値として北マケドニア**が挙げられている。一般的に、離婚率が1,000人当たり3件を超えると、今日の状況では離婚率が高いと見なされる。離婚率の高い国は、急速な社会の自由化や経済の激変により、伝統的な家族の絆が緩んでいることが多い。
- 最も低い割合:もう一方の極端な例では、南アジア諸国と西アフリカ諸国の離婚率が最も低い。インドの~1%の離婚発生率は、強い婚姻永続規範を象徴している。その他に離婚率が非常に低い国(婚姻件数1,000件あたり0.5件未満、または10%未満)には、ブータン、スリランカ、ベトナム、グアテマラ、ペルー、アフリカ諸国がある。これらの国の多くでは、離婚が社会的に、時には法的に奨励されている。さらに、離婚を法的に禁止している州もいくつかあり(フィリピン、バチカン)、事実上離婚率はゼロに保たれている。
- 地域差:ヨーロッパは東部(バルト、スラブ諸国では離婚が非常に多い)、西部/北部(多いがやや減少、減少もある)、南部(中程度、低いベースから上昇)に分かれる。北米/オセアニアは比較的均質で、中程度の高さの離婚が一般的である(結婚の40~50%)。ラテンアメリカは、合法化後は増加傾向にあるが、一般的に離婚率は中程度から低めである。アジアは、東アジアの高水準から南アジアの低水準まで幅があり、東南アジアは中程度である。アフリカは、数カ国が高くなりつつある以外は、概ね低い。このような違いは、多くの場合、各地域の優勢な宗教や文化的歴史、開発水準と一致している。
- 歴史の転換:主要国では、20世紀後半に離婚が大幅に普及したが、「離婚ブーム」は減速している。例えば、米国や多くのヨーロッパ諸国では、衝動的に結婚する人が減り、結婚の質に対する期待が高まるにつれて、離婚率がピーク時から低下している。専門家の中には、結婚する人がより意図的に結婚するようになり、より長続きする結婚につながる可能性がある(いくつかのデータでミレニアル世代の離婚率が低下していることに見られるように)。同時に、世界の他の地域(アジアの一部や中東など)では、近代化が定着するにつれて離婚が増加する時期に入っている。
- 社会的背景:離婚率の高さは、本質的に「良い」「悪い」というわけではない。個人の自由や男女平等の拡大を示すこともあるが(人々は悪い結婚から抜け出すことができる)、社会的ストレスや支援ネットワークの弱体化を反映することもある。離婚率の低さは、安定した家庭と強いコミットメントを示すこともあるが、結婚生活に耐えられない人々には選択肢がないことを示すこともある。例えば、離婚率が非常に低い社会では、非正規の別居が多かったり、代替手段がないために虐待に耐えている女性がいたりする。例えば、スウェーデンでは離婚が多いということは、高い生活満足度と男女平等が共存しているということであり、一方、アフガニスタンでは離婚が少ないということは、女性の自律性が低いということである。
- COVID-19の影響:COVID-19のパンデミックは、当初2020年に離婚件数の減少を引き起こした(裁判所が閉鎖され、夫婦の決断が遅れたため)。その後、2021年から2022年にかけて回復した国もある(英国、米国の一部など)。パンデミックの正味の影響についてはまだ調査中だが、多くの離婚が防止されたというよりは、むしろ遅れたと思われる。また、長期的には離婚を増加させる可能性のある新たなストレス(ロックダウンの葛藤)も導入された。例えば、中国やヨーロッパ諸国からの逸話的証拠によれば、ロックダウン解除直後に離婚申請が急増した。全体として、パンデミックは、外的な出来事が一時的に家族の力学を変化させるが、その後中核的な傾向が再開することを浮き彫りにした。
結論として、世界の離婚率は社会の変化を映し出す鏡である。急速な社会変化(経済発展、性別役割分担の変化、世俗化)の真っ只中にある国では、既成の規範が崩れ、個人が自己実現を優先するため、離婚が増加することが多い。逆に、伝統的な構造を堅持する社会では、それが選択によるものであれ、強制によるものであれ、離婚はまれである。世界が発展し、文化的価値観が進化し続けるにつれて、ある程度までは離婚率が上昇する国が増えるだろう。実際、国連によれば、世界中で離婚/別居している成人の割合は増加しており、1970年代から2000年代にかけて倍増している。極端に離婚率の高い国は(結婚が一般的でなくなったり、より良いマッチングによって関係が強化されるにつれて)安定し、極端に離婚率の低い国は、考え方が自由化されるにつれて徐々に増加するかもしれない。
政策の観点からは、このデータは、夫婦関係の安定と個人の幸福のバランスをとる必要性を示唆している。離婚率の高い社会は、ひとり親家庭を支援し、離婚の子ども(経済的・精神的な影響を受けることが多い)のニーズに対応するという課題に直面している。一方、離婚率の低い社会は、社会的あるいは法的な圧力によって結婚に閉じ込められた個人の権利と福祉を考慮しなければならない。最終的には、恣意的に離婚率を押し上げたり下げたりするのではなく、結婚が自由な選択によって結ばれ、結ばれる仕組みにかかわらず、家族や個人が必要な支援を受けられるようにすることが目標である。ある文化圏では生涯結婚がほぼ普遍的である一方、ある文化圏では結婚がコインの裏表のようなものであるなど、離婚に関する世界的な図式は驚くほど多様であり、最も個人的な制度のひとつである結婚が、それを取り巻く広範な社会によっていかに深く形作られているかを浮き彫りにしている。







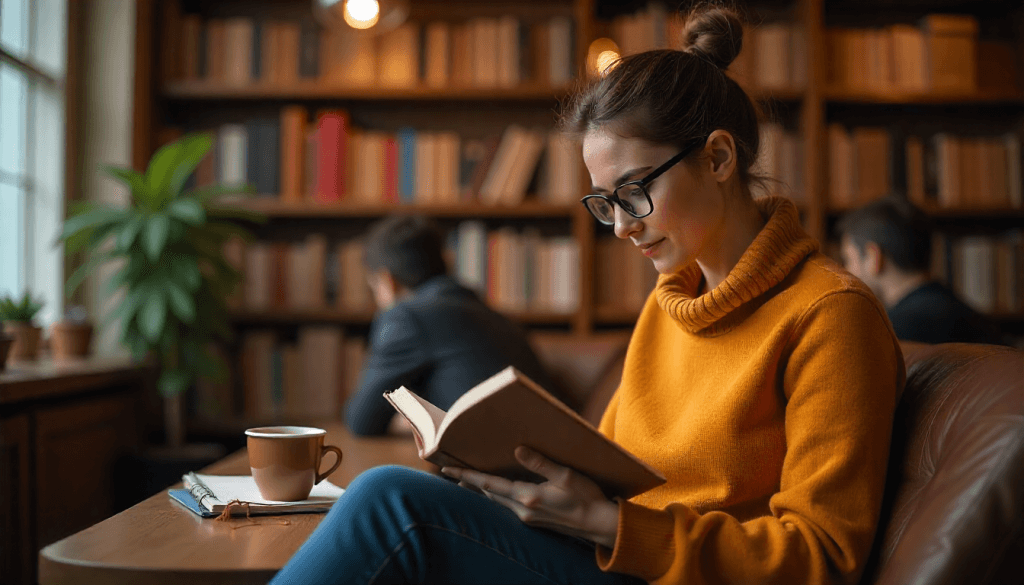





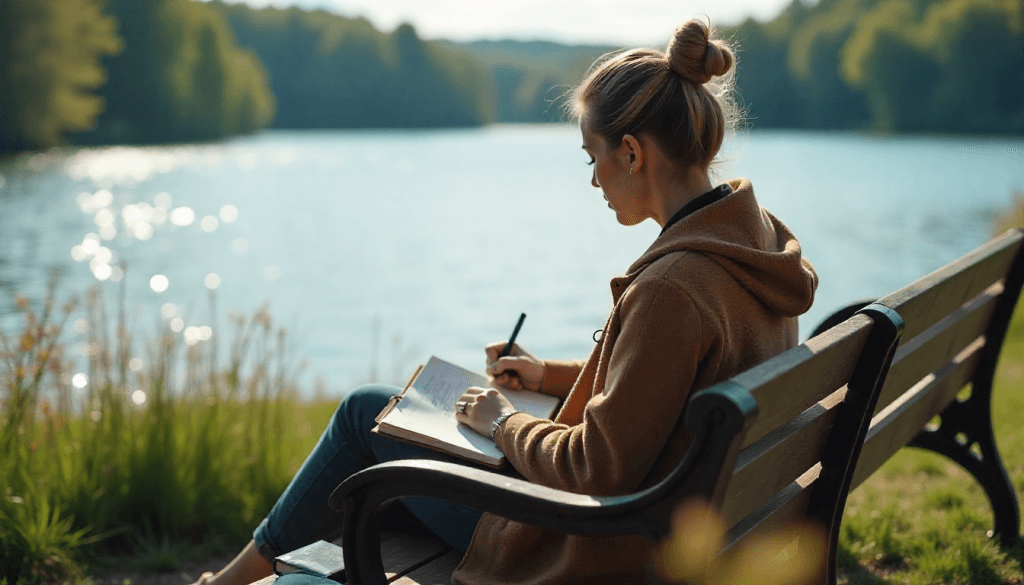
Genial el estudio presentado, muy bien documentado. Gracias.
J’ai un problème pour comprendre